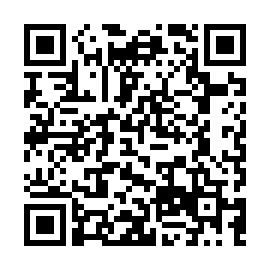名古屋市昭和区の かわな行政書士事務所 です。当事務所では建設業許可申請を中心に各種許認可申請を主な業務としております。
- トップページ
- >
- その他各種申請
各種申請業務一覧
産業廃棄物収集運搬業許可申請
1.許可について
(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、積替え保管施設を有する場合で、それが政令で定める市※にある場合は、政令で定める市の市長の許可もあわせて必要になります。
収集運搬については、収集する区域、運搬先の区域又は積替え保管施設のある区域を管轄する都道府県知事又は政令で定める市の市長の許可が必要です。
運搬の途中で通過するだけの区域については、許可は不要です。
※ 政令で定める市(愛知県内の場合)
名古屋市、豊橋市、豊田市、岡崎市
(3)産業廃棄物の種類
法令に基づき産業廃棄物は以下のように分けられています。
(4)特別管理産業廃棄物の種類
・ 引火性廃油
・ 腐食性廃酸
・ 腐食性廃アルカリ
・ 感染性産業廃棄物
・ 特定有害PCB等
・ 特定有害PCB汚染物
・ 特定有害PCB処理物
・ 特定有害石綿等
・ 特定有害指定下水汚泥
・ 特定有害鉱さい
・ 特定有害ダスト類(ばいじん)
・ 特定有害燃え殻
・ 特定有害廃油
・ 特定有害汚泥
・ 特定有害廃酸
・ 特定有害廃アルカリ
2.廃棄物の種類
(3)産業廃棄物の種類
法令に基づき産業廃棄物は以下のように分けられています。
(4)特別管理産業廃棄物の種類
3.許可の有効期間
(1)産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は次のとおりです。
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は以下のとおりです。
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 74,000円
変更許可申請 72,000円
※ この手数料は、審査のために行政庁に支払う金額です。
当事務所に対する報酬は別途必要になりますので、ご了承ください。
お問い合わせはこちら ≫
(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、積替え保管施設を有する場合で、それが政令で定める市※にある場合は、政令で定める市の市長の許可もあわせて必要になります。
収集運搬については、収集する区域、運搬先の区域又は積替え保管施設のある区域を管轄する都道府県知事又は政令で定める市の市長の許可が必要です。
運搬の途中で通過するだけの区域については、許可は不要です。
※ 政令で定める市(愛知県内の場合)
名古屋市、豊橋市、豊田市、岡崎市
| 2.廃棄物の種類 |
||
| (1) | 廃棄物とは 廃棄物とは法律により「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの※」と定義されています。 ※ 放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。 |
|
| (2) | 廃棄物の分類 廃棄物は法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。 |
|
| ① | 産業廃棄物とは 事業活動に伴って排出される、がれき類、汚泥、廃プラスチック類などの廃棄物です。(下記(3)) さらに、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害が生ずる恐れのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として別に定められています。(下記(4)) |
|
| ② | 一般廃棄物とは 産業廃棄物以外の廃棄物のことを言います。 主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなど。 |
|
| ※ | 事業者は、一般廃棄物と産業廃棄物の区分にかかわらず、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければなりません。 | |
(3)産業廃棄物の種類
法令に基づき産業廃棄物は以下のように分けられています。
| ① | 燃え殻 | ||
| ② | 汚泥 | ||
| ③ | 廃油 | ||
| ④ | 廃酸 | ||
| ⑤ | 廃アルカリ | ||
| ⑥ | 廃プラスチック類 ◎* | ||
| ⑦ | ゴムくず | ||
| ⑧ | 金属くず ◎ | ||
| ⑨ | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず ◎* | ||
| ⑩ | 鉱さい | ||
| ⑪ | がれき類 * | ||
| ⑫ | ダスト類(ばいじん) | ||
| ⑬ | 紙ずく | ||
| ⑭ | 木くず | ||
| ⑮ | 繊維くず | ||
| ⑯ | 動植物性残さ | ||
| ⑰ | 動物系固形不要物 | ||
| ⑱ | 家畜ふん尿 | ||
| ⑲ | 家畜の死体 | ||
| ⑳ | 13号廃棄物 | ||
| 【注意】 | |||
| ・ | ⑬~⑲については、特定の事業活動に伴って生じたものが、産業廃棄物になります。 | ||
| ・ | ◎印の品目には、自動車等破砕物(シュレッダーダスト)を含むか否かの区分があります。 | ||
| ・ | *印の品目には、石綿含有産業廃棄物を含むか否かの区分があります。 | ||
(4)特別管理産業廃棄物の種類
・ 引火性廃油
・ 腐食性廃酸
・ 腐食性廃アルカリ
・ 感染性産業廃棄物
・ 特定有害PCB等
・ 特定有害PCB汚染物
・ 特定有害PCB処理物
・ 特定有害石綿等
・ 特定有害指定下水汚泥
・ 特定有害鉱さい
・ 特定有害ダスト類(ばいじん)
・ 特定有害燃え殻
・ 特定有害廃油
・ 特定有害汚泥
・ 特定有害廃酸
・ 特定有害廃アルカリ
2.廃棄物の種類
| (1) | 廃棄物とは 廃棄物とは法律により「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの※」と定義されています。 ※ 放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。 |
|
| (2) | 廃棄物の分類 廃棄物は法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。 |
|
| ① | 産業廃棄物とは 事業活動に伴って排出される、がれき類、汚泥、廃プラスチック類などの廃棄物です。(下記(3)) さらに、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害が生ずる恐れのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として別に定められています。(下記(4)) |
|
| ② | 一般廃棄物とは 産業廃棄物以外の廃棄物のことを言います。 主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなど。 |
|
| ※ | 事業者は、一般廃棄物と産業廃棄物の区分にかかわらず、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければなりません。 | |
(3)産業廃棄物の種類
法令に基づき産業廃棄物は以下のように分けられています。
| ① | 燃え殻 | ||
| ② | 汚泥 | ||
| ③ | 廃油 | ||
| ④ | 廃酸 | ||
| ⑤ | 廃アルカリ | ||
| ⑥ | 廃プラスチック類 ◎* | ||
| ⑦ | ゴムくず | ||
| ⑧ | 金属くず ◎ | ||
| ⑨ | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず ◎* | ||
| ⑩ | 鉱さい | ||
| ⑪ | がれき類 * | ||
| ⑫ | ダスト類(ばいじん) | ||
| ⑬ | 紙ずく | ||
| ⑭ | 木くず | ||
| ⑮ | 繊維くず | ||
| ⑯ | 動植物性残さ | ||
| ⑰ | 動物系固形不要物 | ||
| ⑱ | 家畜ふん尿 | ||
| ⑲ | 家畜の死体 | ||
| ⑳ | 13号廃棄物 | ||
| 【注意】 | |||
| ・ | ⑬~⑲については、特定の事業活動に伴って生じたものが、産業廃棄物になります。 | ||
| ・ | ◎印の品目には、自動車等破砕物(シュレッダーダスト)を含むか否かの区分があります。 | ||
| ・ | *印の品目には、石綿含有産業廃棄物を含むか否かの区分があります。 | ||
(4)特別管理産業廃棄物の種類
| ・ | 引火性廃油 | |
| ・ | 腐食性廃酸 | |
| ・ | 腐食性廃アルカリ | |
| ・ | 感染性産業廃棄物 | |
| ・ | 特定有害PCB等 | |
| ・ | 特定有害PCB汚染物 | |
| ・ | 特定有害PCB処理物 | |
| ・ | 特定有害石綿等 | |
| ・ | 特定有害指定下水汚泥 | |
| ・ | 特定有害鉱さい | |
| ・ | 特定有害ダスト類(ばいじん) | |
| ・ | 特定有害燃え殻 | |
| ・ | 特定有害廃油 | |
| ・ | 特定有害汚泥 | |
| ・ | 特定有害廃酸 | |
| ・ | 特定有害廃アルカリ |
3.許可の有効期間
| 許可の有効期間は5年です。 許可を継続するためには、有効期間が満了する前に更新の手続きをする必要があります。 |
(1)産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は次のとおりです。
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は以下のとおりです。
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 74,000円
変更許可申請 72,000円
※ この手数料は、審査のために行政庁に支払う金額です。
当事務所に対する報酬は別途必要になりますので、ご了承ください。
お問い合わせはこちら ≫
宅地建物取引業免許申請
1. 概要と免許が必要な方
宅地建物取引業とは
2. 免許の区分
免許の区分には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。
3. 申請の流れ(愛知県知事免許の場合)
4. 免許の有効期間
宅地建物取引業免許の有効期間は、免許のあった日の翌日から5年目の免許があった日までです。有効期間の満了日が日曜日等であってもの、その日が免許の満了日となるので注意が必要です。
5. 申請手数料
愛知県収入証紙 ・・・ 33,000円
※ 当事務所に対する報酬は別途必要です。
6. 審査基準および要件
※ 実際の申請には他にも細かい要件がありますので、ご相談ください。
お問い合わせはこちら ≫
宅地建物取引業とは
| ① | 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと | |
| ② | 若しくは媒介することを業として行うこと ⇒ すなわち、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して下表の○印の行為を反復継続して行い、それが社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものの場合は免許が必要です。 |
|
| 区分 |
自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃貸 | ☓ | ○ | ○ |
2. 免許の区分
免許の区分には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。
| ・ 国土交通大臣免許 | 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合に必要 | |
| ・ 都道府県知事免許 | 1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合に必要 | |
3. 申請の流れ(愛知県知事免許の場合)
| ① | 書類の提出 申請書および添付書類を愛知県 建設業不動産業課 不動産グループ に提出します。 |
| ② | 審査 書類が受理されると、内容を審査されます 審査期間は、書類に不備がない場合で、概ね30日~50日程度です。(状況により延長の場合あり) |
| ③ | 免許の通知 通常ハガキにより通知されます。 |
| ④ | 営業保証金の供託または保証協会への加入 免許を取得しても、法務局へ営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。 |
| 営業保証金について |
||
| 主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。 | ||
| 宅地建物取引業保証協会への加入について | ||
| 保証協会への加入手続きは及び必要経費などは、各団体にお問い合わせください。 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 愛知県本部 http://www.aichi-takken.or.jp/ 社団法人 不動産保証協会 愛知県本部 http://aichi.zennichi.or.jp/ |
||
| ⑤ | 供託済証の届出 愛知県建設業不動産業課に営業保証金供託済届出書を提出します。 |
| ⑥ | 免許の交付 上記の手続きが完了した後に免許交付され、営業することが可能になります。 |
4. 免許の有効期間
宅地建物取引業免許の有効期間は、免許のあった日の翌日から5年目の免許があった日までです。有効期間の満了日が日曜日等であってもの、その日が免許の満了日となるので注意が必要です。
| ⇒ | つまり5年毎に免許の更新手続きが必要ということです。 免許の更新申請は、期間満了日の90日前から受け付けられ、期間満了日の30日前までに行うことが必要です。 |
|
5. 申請手数料
愛知県収入証紙 ・・・ 33,000円
※ 当事務所に対する報酬は別途必要です。
6. 審査基準および要件
| ① | 法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。 |
| ② | 継続的に業務を行うことができ、かつ独立性が保たれている事務所が必要です。 |
| ③ | 従たる事務所(支店)など代表者が常勤できない事務所には、政令で定める使用人を設置しなければなりません。政令使用人はその事務所の代表者であり、契約を締結する権限を有し、その事務所に常勤していることが必要です。 |
| ④ | 宅地建物取引士証の交付を受けた専任の宅地建物取引士を、1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、設置することが必要です。 |
| ⑤ | 代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当していないことが必要です。 |
※ 実際の申請には他にも細かい要件がありますので、ご相談ください。
お問い合わせはこちら ≫
建築事務所登録申請
1. 概要
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより、知事へ登録申請しなければなりません。
2. 新規に建築士事務所登録をされる方について
建築士事務所には専任の管理建築士を置かなければなりません。
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後に受講できる管理建築士講習修了証をお持ちの管理建築士がいない場合は、登録できませんのでご注意ください。
3. 申請窓口について
建築士事務所の新規登録、更新登録、登録事項の変更、廃止、登録証明は、愛知県指定事務所登録機関である(社)愛知県建築士事務所協会で行います。
また、建築士事務所の業務に関する報告書の提出についても(社)愛知県建築士事務所協会への提出になります。
⇒社団法人 愛知県建築士事務所協会 http://www.aichi-jimkyo.or.jp/
4. 建築士事務所の登録等手数料について
※ 当事務所に対する報酬は別途必要です。
5. 事務所登録事務の処理期間
新規登録・更新登録に14日間、登録事項変更・廃業及び抹消・取消等の処分・登録証明発行はすみやかに行われます。
新規登録・更新登録場合は登録完了後、申請書副本とともに登録通知書が申請者宛に送付されます。
6. 登録の有効期間および更新について
建築士事務所登録の有効期限は、登録年月日の5年後の前日までです。
引き続き業務を行う場合、有効期限満了日の2ヶ月前~30日前までの間に、更新手続きを行って下さい。
なお、更新日が近づいた旨の連絡は建築士事務所協会からはありませんので、ご注意下さい。
お問い合わせはこちら ≫
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより、知事へ登録申請しなければなりません。
2. 新規に建築士事務所登録をされる方について
建築士事務所には専任の管理建築士を置かなければなりません。
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後に受講できる管理建築士講習修了証をお持ちの管理建築士がいない場合は、登録できませんのでご注意ください。
3. 申請窓口について
建築士事務所の新規登録、更新登録、登録事項の変更、廃止、登録証明は、愛知県指定事務所登録機関である(社)愛知県建築士事務所協会で行います。
また、建築士事務所の業務に関する報告書の提出についても(社)愛知県建築士事務所協会への提出になります。
⇒社団法人 愛知県建築士事務所協会 http://www.aichi-jimkyo.or.jp/
4. 建築士事務所の登録等手数料について
| ア.一級建築士事務所登録手数料 |
16,000円 |
| イ.二級・木造建築士事務所登録手数料 |
11,000円 |
| ウ.建築士事務所登録証明発行手数料 |
400円 |
※ 当事務所に対する報酬は別途必要です。
5. 事務所登録事務の処理期間
新規登録・更新登録に14日間、登録事項変更・廃業及び抹消・取消等の処分・登録証明発行はすみやかに行われます。
新規登録・更新登録場合は登録完了後、申請書副本とともに登録通知書が申請者宛に送付されます。
6. 登録の有効期間および更新について
建築士事務所登録の有効期限は、登録年月日の5年後の前日までです。
引き続き業務を行う場合、有効期限満了日の2ヶ月前~30日前までの間に、更新手続きを行って下さい。
なお、更新日が近づいた旨の連絡は建築士事務所協会からはありませんので、ご注意下さい。
お問い合わせはこちら ≫
電気工事業者登録申請
1.電気工事業の登録等
| 電気工作物による感電、電気火災の危険の発生を防止するため、電気工事業を営む者の登録等とその規制が、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)に定められています。 |
電気工事業の登録、通知、届け出
| 電気工事業を営もうとする者(法人及び個人)は、電気工事業の登録、通知、又は届け出をしなければなりません。 電気工事業者は、施工する電気工事の種類や建設業の許可を受けた建設業者であるかどうかにより、次の4種類の事業者に分類されます。 |
| ① | 登録電気工事業者 一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。 この制度により登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。 登録の有効期間は5年で、有効期間満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は、更新登録を受けなければなりません。 |
|
| ② | 通知電気工事業者 500Kw未満の自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣または都道府県知事に通知しなければなりません。 この制度により通知した方を「通知電気工事業者」といいます。 |
|
| ③ | みなし登録電気工事業者 建設業法の許可を受けた建設業者(建設業法第2条第3項)であって、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、登録をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。 ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなり、遅滞なくその旨を経済産業大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。 |
|
| ④ | みなし通知電気工事業者 建設業法の許可を受けた建設業者(建設業法第2条第3項)であって、500Kw未満の自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通知をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。 ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の通知の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなり、遅滞なくその旨を経済産業大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。 |
電気工事業者は、その業務に関し次の事項を守らなければなりません。
| (1) | 主任電気工事士の設置(法第19条第1項) 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所(特定営業所)ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であって、電気工事業法等に違反して いないなどの所定の要件を満たす者を、主任電気工事士として置かなければなりません。 なお、主任電気工事士が欠けるに至ったとき等は、知った日から2週間以内に、主任電気工事士の選任をしなければなりません。 |
| (2) | 主任電気工事士の職務 主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。 また、一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければなりません。 |
| (3) | 電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止 登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。 電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事を除く。)の作業に従事させてはなりません。 ただし、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができます。 電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者でない者をその特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。 |
| (4) | 電気工事を請け負わせることの制限 電気工事業者は、その請け負った電気工事をその電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。 |
| (5) | 電気用品の使用の制限 電気工事業者は、電気用品安全法に規定する表示が付されている電気用品でなければ、 これを電気工事に使用してはなりません。 |
| (6) | 器具の備付 電気工事業者は、その営業所ごとに、電気工事の検査に必要な器具を備え付けなければなりません。 |
|
| ① | 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 | |
| ② | 自家用電気工事の業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。) | |
| (7) | 標識の掲示 電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所(電気工事が1日で完了する場合を 除く)ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。 |
||
| 1. | 登録電気工事業者 ① 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 ② 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ③ 登録の年月日及び登録番号 ④ 主任電気工事士等の氏名 |
||
| 2. | 通知電気工事業者 ① 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 ② 営業所の名称 ③ 法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先 |
||
| 3. | みなし登録電気工事業者 ① 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 ② 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ③ 法第34条第4項の規定による届出の年月日及び届出先 ④ 主任電気工事士等の氏名 |
||
| 4. | みなし通知電気工事業者 ① 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 ② 営業所の名称 ③ 法第34条第5項の規定による通知の年月日及び通知先 |
||
| (8) | 帳簿の備付け 電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載し、 これを5年間保存しなければなりません。 ① 注文者の氏名又は名称及び住所 ② 電気工事の種類及び施工場所 ③ 施工年月日 ④ 主任電気工事士等及び作業者の氏名 ⑤ 配線図 ⑥ 検査結果 |
| 電気工事業者は次に掲げる届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく、電気工事業に係る変更届出書を提出しなければなりません。 ① 氏名または名称(法人の組織変更を含む。) ② 住所(住居表示の変更を含む。) ③ 電気工事の種類 ④ 営業所の名称 ⑤ 営業所の所在の場所 ⑥ 営業所の増設・廃止 ⑦ 主任電気工事士の氏名 ⑧ 主任電気工事士の電気工事免状の種類および交付番号 ⑨ 法人の代表者 ⑩ 建設業許可の更新 |
お問い合わせはこちら ≫
解体工事業者登録申請
1.解体工事業の登録とは
お問い合わせはこちら ≫
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という。)の規定により、解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた方については登録不要です。 |
| (1) | 解体工事業が必要な方とは? |
| ① 以下のいずれかの建設業の許可を持っている。 土木工事業 建築工事業 とび・土工工事業 はい ⇒ 登録は不要です。 いいえ ⇒ ②へ ② 500万円以上の解体工事を請け負う。 はい ⇒ 建設業の許可が必要です。 いいえ ⇒ 解体工事業の登録が必要です。 ※ 登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行います。 ※ 複数の都道府県で解体工事を行おうとする方は、各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。 |
| (2) | 解体工事業の登録に関する要件 | ||
| ① 法律に定める欠格要件に該当しないこと | |||
| ア. | 登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合 | ||
| イ. | 解体工事業者としての適性を期待し得ない場合 | ||
| a. | 法の規定(第35条第1項)により解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者 | ||
| b. | 解体工事業者で法人であるものが法(第35条第1項)の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 | ||
| c. | 法の規定(第35条第1項)により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 | ||
| d. | 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | ||
| e. | 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記a~dに該当するとき | ||
| f. | 法人でその役員※のうちに上記a~dまでのいずれかに該当する者がある者 | ||
| g. | 技術管理者を選任していない者 | ||
※役員・・・業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 |
|||
| ② | 技術管理者を選任していること 解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。 ただし、技術管理者は下記の国土交通省令で定める基準に適合しているものでなければなりません。 |
||
| (1) | 登録申請に必要な書類 | ||
| ① | 解体工事業登録申請書(別記様式第1号|記載例) | ||
| ② | 誓約書(別記様式第2号|記載例) | ||
| ③ | 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面(表1参照) | ||
| a. | 卒業証明書 | ||
| b. | 実務経験証明書(別記様式第3号|記載例) | ||
| c. | 国家資格証 | ||
| d. | 講習修了証 | ||
| e | 登録試験合格証等 (「(社)全国解体工事業団体連合会、(株)日本解体工事技術協会」実施) |
||
| ④ | 登録申請者(法人は役員全員、個人は本人。以下同じ。)の略歴書(法定代理人を含む。) (別記様式第4号|記載例-個人事業主|記載例-法人の役員)なお、法人にあっては法人自体の略歴書(記載例)も必要となります。 | ||
| ⑤ | 登記事項証明書(法人の場合に限る。) | ||
| ⑥ | 解体工事業登録申請書提出票(愛知県様式) | ||
※ 住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認情報の提供が受けられない場合は、以下の書類も必要となります |
|||
| ・ | 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | ||
| ・ | 登録申請者が「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合」は、その法定代理人に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面 | ||
| ・ | 技術管理者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | ||
| ※ | 登記事項証明書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面は、申請直前3ヶ月以内に取得の原本を提出してください。(副本は写し可) なお、登録の更新を受けようとする方にあっては、有効期間満了の日の3ヶ月前から有効期間満了の日の30日前までに更新申請書類を提出してください。 | ||
(2)登録に関する手数料
新規申請・・・33,000円
更新申請・・・26,000円
手数料は愛知県収入証紙にて納付することになります。
※ 当事務所に対する報酬は別途必要になります。
| (1) | 登録の有効期間 登録の有効期間は、5年間です |
|
| (2) | 登録事項に変更があった場合 以下の登録事項にに変更があった場合は、30日以内に「解体工事業登録事項変更届出書」の提出が必要です。 |
|
| ・ | 商号、名称又は氏名及び住所に変更があった場合 | |
| ・ | 営業所の名称及び所在地に変更があった場合 | |
| ・ | 法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方)に変更があった場合 | |
| ・ | 法定代理人の氏名及び住所に変更があった場合 | |
| ・ | 技術管理者に変更があった場合 | |
| (3) | 解体工事を廃業した場合 以下の場合は、30日以内に解体工事業廃業等届出書の提出が必要です。 |
|
| ・ | 個人事業主の解体工事業者が死亡したとき | |
| ・ | 法人が合併により消滅したとき | |
| ・ | 法人が破産手続開始の決定により解散したとき | |
| ・ | 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | |
| ・ | 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | |
| (4) | 通知書について 解体工事業登録後に、建設業法第3条第1項の土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた場合は、30日以内に通知書の提出が必要です。 |
|
| (5) | 登録証明書について 愛知県知事による解体工事業の登録を受けた方は、ご自分が愛知県知事による登録業者であることの証明を受けることができます。 登録証明をご希望の方は、解体工事業登録証明願と解体工事業登録証明書(愛知県様式)の双方に必要事項を記入し、それぞれ所管する部所に申請してください。 |
|
| (6) | 標識の掲示 解体工事業者は営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識(別記様式第7号)を掲げなければなりません。 |
|
| (7) | 帳簿の備付け等 解体工事業者は、営業所及び請負った解体工事ごとに営業に関する事項を記載した帳簿(別記様式第8号)を作成し、建設業法第19条第1項及び第2項に規定する契約書又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し)を添付しなければなりません。 帳簿及び添付書類は、請負った解体工事ごとに、その工事の完了の日が属する事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。 |
|
お問い合わせはこちら ≫
古物商許可申請
1.古物商とは
2.古物とは
3.許可の要件
4.許可申請に必要な書類
5.許可申請の手数料
古物営業許可申請手数料 19,000円
※当事務所に対する報酬は別途必要です。
6.変更届出書について
※ 許可証の記載事項に変更がある場合は、書換申請書も必要となります。
お問い合わせはこちら ≫
| 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業のことをいいます。 古物の売買等(古物営業)は、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。 古物営業の許可申請をして、許可を受けたものを「古物商」といいます。 |
| (1) | 『古物』とは以下のもののことをいいます。 | |
| ・ | 一度使用された物品 | |
| ・ | 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの | |
| ・ | これらの物品に幾分の手入れをしたもの | |
| (2) | 古物営業法施行規則では、取り扱う古物は次のように区分されています。 | |
| ・ | 『美術品類』 書画、彫刻、工芸品等 |
|
| ・ | 『衣類』 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
|
| ・ | 『時計・宝飾品類』 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
|
| ・ | 『自動車』 その部分品を含みます。 |
|
| ・ | 『自動二輪車及び原動機付自転車』 これらの部分品を含みます。 |
|
| ・ | 『自転車類』 その部分品を含みます。 |
|
| ・ | 『写真機類』 写真機、光学器等 |
|
| ・ | 『事務機器類』 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、 事務用電子計算機等 |
|
| ・ | 『機械工具類』 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
|
| ・ | 『道具類』 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
|
| ・ | 『皮革・ゴム製品類』 カバン、靴等 |
|
| ・ | 『書籍』 | |
| ・ | 『金券類』 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
|
3.許可の要件
| 申請者が次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。 |
|||
| ① | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | ||
| ② | 錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 | ||
| ③ | 住居の定まらない者 | ||
| ④ | 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 | ||
| ⑤ | 法定代理人が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき | ||
| ⑥ | 法人の役員が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき | ||
| ・ | 許可申請書 | |
| ・ | 定款及び登記簿の謄本 法人のみ必要 |
|
| ・ | 最近5年間の略歴を記載した書面 法人の場合は役員について必要 |
|
| ・ | 住民票(外国人登録証明書)の写し 法人の場合は役員について必要 |
|
| ・ | 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 法人の場合は役員について必要 |
|
| ・ | 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書 成年被後見人又は保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 法人の場合は役員について必要 |
|
| ・ | 市区町村長の発行する身分証明書 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(本籍地の市町村長で発行) 法人の場合は役員について必要 |
|
| ・ | URLの使用権限を疎明する資料 ホームページを利用して取引をする場合に必要 |
|
| ※ | 許可申請の単位は、営業所単位ではなく都道府県単位です。 | |
| ※ | 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。 | |
| ※ | 質屋営業の許可を受けた営業者の方が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類を省略できる場合があります。 |
5.許可申請の手数料
古物営業許可申請手数料 19,000円
※当事務所に対する報酬は別途必要です。
6.変更届出書について
| 許可証に記載されている事項や、営業の内容に変更が生じた場合は、許可証の書換申請や変更届を提出しなければなりません。 <変更届が必要な例> |
||
| (1) | 個人の場合で、営業者の氏名又は住所の変更の場合 | |
| (2) | 法人の名称又は所在地の変更の場合 | |
| (3) | 法人の種別を変更した場合 | |
| (4) | 法人の場合で、役員以外の者が、代表者や役員に就任する場合 | |
| (5) | 役員の辞任や、役員が代表者に就任する等の場合 | |
| (6) | 法人の代表者等の氏名又は住所の変更の場合 | |
| (7) | 営業所を新設又は管理者を変更した場合 | |
| (8) | ホームページを新たに開設したり、URLを変更する場合 | |
お問い合わせはこちら ≫